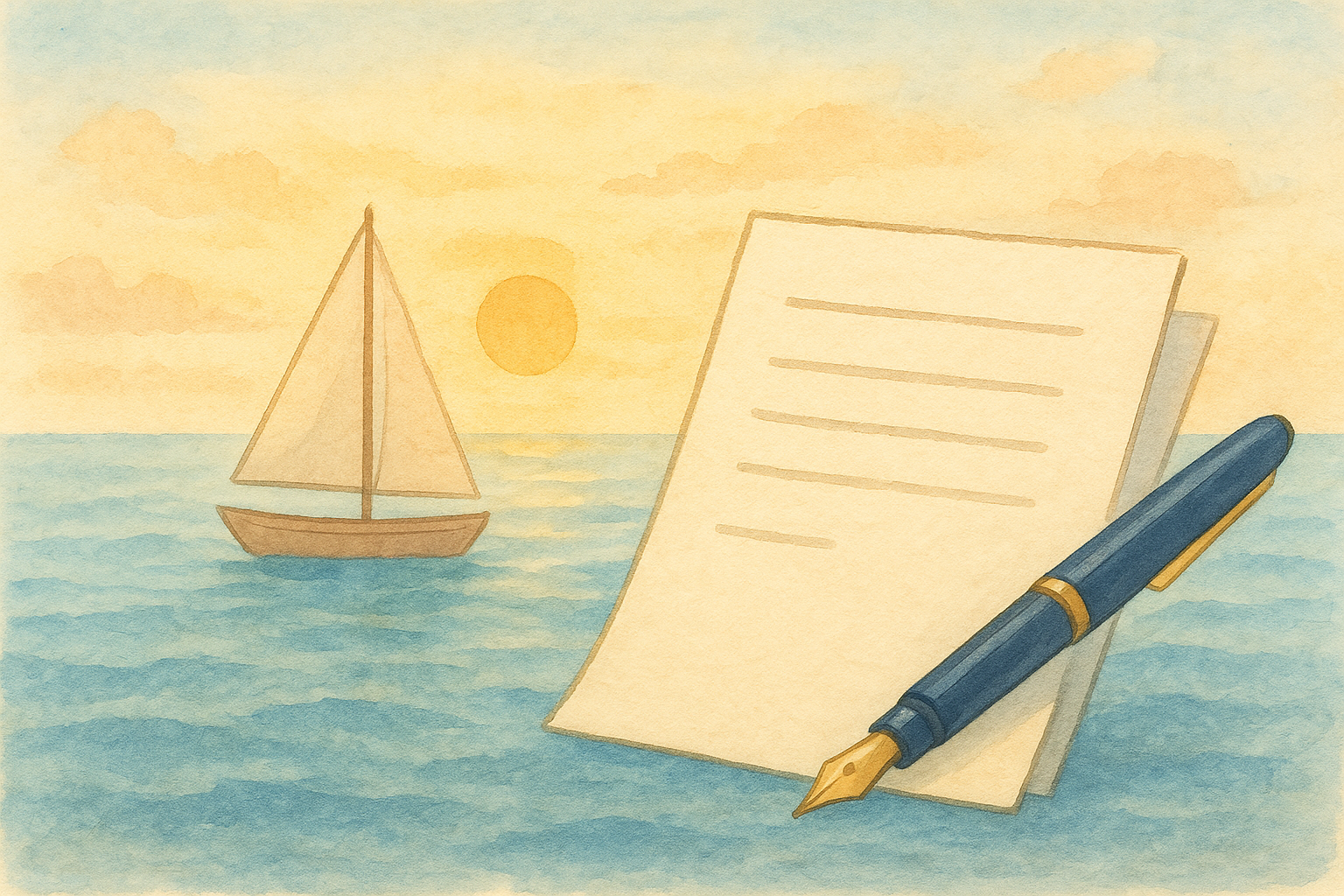士業の職印って何を使えばいいの?4つのポイントをわかりやすく解説
職印とは?
職印とは士業(特に弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・弁理士・公認会計士の8士業)が、業務を行う際に書類に押す印鑑のことです。
その士業によりますが、弁護士・行政書士・海事代理士等登録の際に
印鑑(印章)の登録が必須な士業もあります。
選ぶ時のポイント
職印を選ぶ(作る)ときに大切なポイントは4つあり
- 形(丸印か角印か)を決める
- サイズを決める
- 印影(印鑑に彫る内容)・字体(フォント)を決める
- 素材を決める
です。それぞれ詳しく見ていきましょう
1.形(丸印か角印か)を決める
職印は四角の角印と、丸い丸印があります。
士業で用いる職印であれば、それぞれ決められている場合もあり、
例えば、
2.サイズを決める
丸印にするか、角印にするか決まったら次はサイズを決めなければなりません。
サイズについても、士業では決まっている場合もあるので
詳しくは「登録の案内」等を参照ください。
一般的には、
丸印:16.5~21.0mm
角印:21.0~27.0mm
が目安となりますが、この後決める印影や字体との兼ね合いで
出来る限り見やすい、分かりやすいを念頭に決めるといいでしょう。
なお、士業でも事務所印を別に用意する場合、
丸印のほうが小さくなるように作成したほうが見栄えが良くなる場合が多いです。