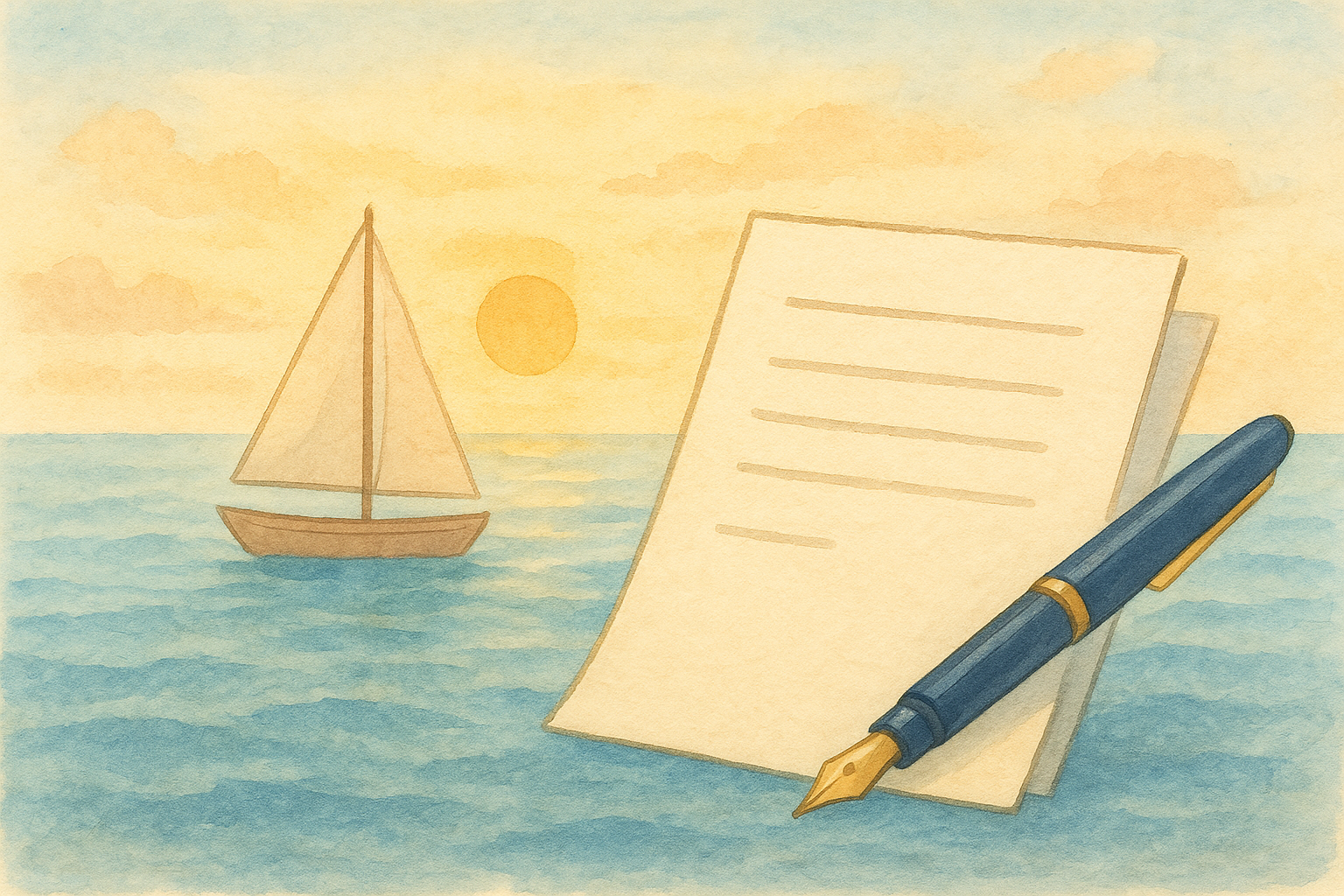海事代理士ってなに?4つのポイントでわかりやすくサクッと解説!
- 海事代理士って何をする人?誰でもなれるの?
- 弁護士や税理士、行政書士との違いは?
- どんな試験?難易度は?
- 求人はあるの?年収はどれくらい?
1.海事代理士って何をする人?誰でもなれるの?
あまり聞き慣れないであろう「海事代理士」について簡単に説明します。
海事代理士(かいじだいりし)とは、海や船に関するさまざまな手続きを、船主や事業者に代わって行う国家資格者です。
国土交通大臣の許可を受けた専門家として、船舶の登録・登記、船員に関する届出、海運業の許認可申請など、海事行政手続きのプロフェッショナルとして活動しています。
たとえば、以下のような業務を行います:
- 船舶の新造・売買・相続に伴う登録や登記の申請
- 海運業・港湾運送事業などの許可申請や更新手続き
- 海技士免許や小型船舶免許に関する申請の代行
- 海事関係の法令・制度に関するコンサルティング
これらの手続きは専門的で煩雑なものが多いため、海事代理士が代行することで、迅速かつ正確な申請を行うことができます。
海運業界・造船業界・マリンレジャー業界など、幅広い分野で活躍する「海の法律専門家」といえる存在です。
試験については後ほど詳しくお伝えしますが、「受験資格」はありません。
つまり、必要なことは「試験に合格」し、「登録する」のみです。
なお、「海事代理士として業務を行う為の(国土交通省への)登録」は必須ですが、
「日本海事代理士会への登録」は必須ではありません。
詳しく知りたい方は、
2.弁護士や税理士、行政書士等の8士業との違いは?
一般的に海事代理士を含め、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・弁理士・公認会計士の8つの資格を総称して、「8士業」と言います。
海事代理士と他士業との比較としては、
弁護士:法律トラブルの専門家(裁判もOK)
行政書士:官公庁に出す書類の専門家
海事代理士:その「海版」。船と海の行政手続専門家
などが挙げられます。
詳しく知りたい方は、
3.どんな試験?難易度は?
海事代理士試験は1次(筆記)と2次(口述)があります。
◯1次試験:筆記試験
〇出題科目について
1次試験は全20科目出題され、全てが1日で終了する試験です。
科目は
・一般法令知識
①憲法
②民法
③商法(第3編「海商」のみ対象。)
・海事関係科目
①国土交通省設置法
②船舶法
③船舶安全法
④船舶のトン数の測度に関する法律
⑤船員法
⑥船員職業安定法
⑦船舶職員及び小型船舶操縦者法
⑧海上運送法
⑨港湾運送事業法
⑩内航海運業法
⑪港則法
⑫海上交通安全法
⑬造船法
⑭海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
⑮国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(国際港湾施設に係る部分を除く。)
⑯領海等における外国船舶の航行に関する法律
⑰船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律及びこれらの法律に基づく命令。)
に分けられます。
20科目と聞くと膨大なイメージですが、過去問からの出題も多く、
1科目当たりの配点、時間も多くはありません。
〇配点・合格点について
1次試験は全20科目のうち、
上記で赤字のものが各20点(20点× 4科目=80点)
それ以外のものが各10点 (10点×16科目=160点)
合計240点満点です。
また、合格点については
令和6年海事代理士試験実施状況について
【筆記試験】
出 願 者 数 578 名
受 験 者 数 441 名
合 格 者 数 229 名
受験者に対する合格率 51.9%
受験者の平均正答率 59.3%
※ 筆記試験の合格基準は 20 科目の総得点 240 点の 60 パーセント以上の得点をあげた者としており、全科目受験者の平均正答率が 60 パーセントを上回る場合には、平均正答率以上の得点をあげた者を合格とすることとしております。
国土交通省HP「海事代理士になるには(https://www.mlit.go.jp/about/file000049.html)」より引用
となっており。
詳しくは、、、
◯2次試験:口述試験
あ
4.求人はあるの?年収はどれくらい?
海事代理士は一般的に開業・起業向けの資格で、求人はほぼありません。
また、開業する人も「海事代理士のみで開業」というより、
行政書士や社会保険労務士等他の士業とのダブルライセンスで
事務所経営されている方が多いです。
まとめ
海事代理士についてまとめると
- 海事代理士試験に受験資格はなく、誰でも受験可能。
- 「試験に合格」し、「登録」をすれば実務を行うことができる。
- 「海事代理士」は「行政書士」や「社会保険労務士」の海版。
- 試験は一般法令科目と海事関係科目で合計20科目ある長丁場試験。
- 一般的な求人はほぼなく、「行政書士」や「社会保険労務士」との
ダブルライセンスで開業する人がほとんど。
こちらの記事もおすすめ